※この記事はPRを含みます
「麻酔導入の時、薬剤の順番がわからなくて焦った」
「麻酔科医の指示が早くて、どのタイミングで何を準備すべきかわからなかった」
そんな経験をしたことがある手術室看護師は多いのではないでしょうか。
全身麻酔薬の投与順番を理解するには、「麻酔薬の特徴」や「全身麻酔の流れ」を把握しておくことが重要です。
この記事では、全身麻酔薬の投与順序と、それぞれの薬剤の役割・安全管理のポイントを、手術室看護師の立場から丁寧に解説します。
この記事をよむメリット💡
✅ 全身麻酔導入時の薬剤の流れを理解できる
✅ 各薬剤の目的と注意点を整理できる
✅ 麻酔導入中に看護師が意識すべき安全確認のコツをつかめる
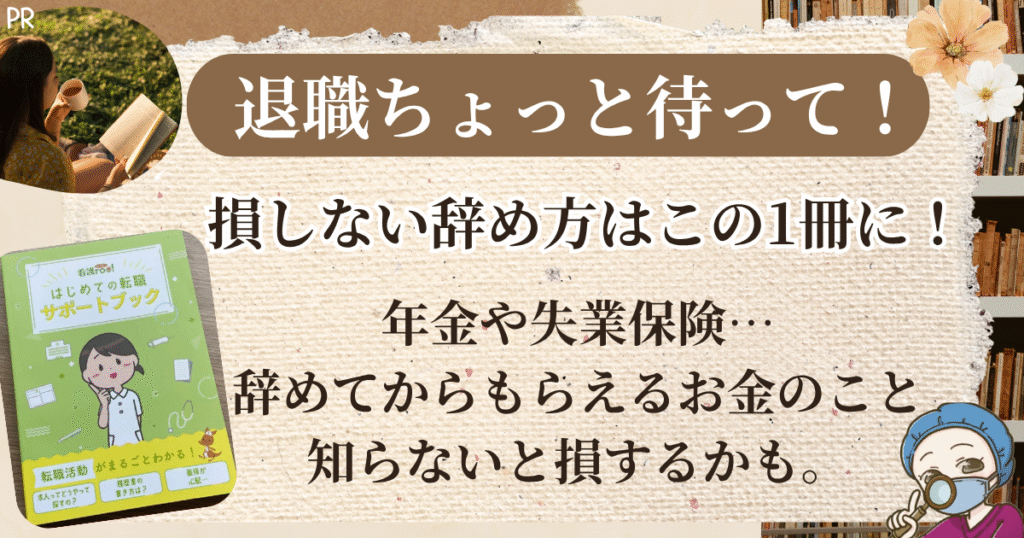
辞めたくなったら。後悔する前に☺️👆
全身麻酔薬の投与順番 ― 麻酔導入の手順とともに解説💡
全身麻酔導入の流れは、原則として次の6ステップで進みます。
| ステップ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| ① 前酸素化 | 100%酸素を吸入させる | 無呼吸に備え酸素予備能を高める |
| ② 鎮痛薬投与 | オピオイドを投与 | 痛覚抑制・血圧上昇の防止 |
| ③ 鎮静薬投与 | プロポフォールなど | 意識を消失させる |
| ④ マスク換気確認 | 換気の可否を評価 | 安全な挿管準備 |
| ⑤ 筋弛緩薬投与 | ロクロニウムなど | 気管挿管を容易にする |
| ⑥ 気管挿管 | チューブを挿入 | 呼吸管理を確立する |
それぞれのステップに看護師が関わるべきポイントを、順に解説していきます。
前酸素化 ― 「脱窒素化」で時間を稼ぐ
麻酔導入の最初のステップは、100%酸素で3分間吸入する「前酸素化」。
これは、肺の中にある窒素を酸素に置き換えることで、無呼吸になっても酸素が体内に残る時間を延長する目的があります。
ここで重要なのは、フェイスマスクの密着です。マスクリークがあると十分な前酸素化ができません。
頭部を少し後屈させる「スニッフィングポジション」をとり、顎を軽く上げて呼吸しやすい姿勢を整えましょう。
鎮痛薬の投与 ― 有害反射を抑える
次に投与されるのが鎮痛薬(オピオイド)です。代表的なのはフェンタニルやレミフェンタニル。
これらは、挿管刺激による血圧上昇や頻脈を防ぐほか、プロポフォール投与時の血管痛の緩和にも役立ちます。
看護師は、投与直後に呼吸抑制や咳嗽反応が起きていないか観察することが大切です。特にレミフェンタニルは即効性が高いため、患者が意識を保っているタイミングでの急速投与は避けるように注意します。
鎮静薬の投与 ― 意識を落とすタイミング
鎮痛薬の効果が出始めたら、鎮静薬(催眠薬)の投与です。
現在最も多く使用されるのはプロポフォール。投与後10秒程度で眠りに入り、呼吸が弱まります。
看護師が確認すべきポイントは、睫毛反射の消失。まつげを軽く触れてまぶたが動かなくなれば、意識消失を意味します。
ここで注意したいのが、血圧低下や呼吸停止です。プロポフォールは強い循環抑制作用があるため、麻酔科医の指示に合わせて血圧モニタリングや換気準備を整えておくことが重要です。
マスク換気の確認 ― 「V1」を確保する
鎮静薬によって呼吸が止まったら、フェイスマスクで換気を開始します。
このとき、しっかり胸郭が動いているか、呼気CO₂波形(カプノグラム)が描けているかを確認します。
日本麻酔科学会では、換気の状態を「V1〜V3」に分類しています。
- V1:換気良好(安全)
- V2:換気困難(準緊急)
- V3:換気不能(緊急)
筋弛緩薬を投与する前に、必ずV1であることを確認するのが安全の鉄則です。
筋弛緩薬の投与 ― 換気ができてから
筋弛緩薬(ロクロニウムなど)は、呼吸筋も含めて全身の筋肉を弛緩させます。
そのため、マスク換気ができない状態で投与するのは極めて危険です。
ロクロニウム投与後は、作用発現まで約1〜2分。この間もマスク換気を続け、換気の維持を確認します。
最近では、拮抗薬のスガマデクスの存在により「導入初期からロクロニウムを早めに投与する」方法も一部で採用されていますが、看護師は換気評価を優先する姿勢を忘れてはいけません。
気管挿管 ― 深麻酔下で安全に
筋弛緩が十分に効いたことを確認し、いよいよ気管挿管を行います。
麻酔科医が喉頭鏡を挿入する際、看護師は頭部固定・体動防止をサポート。
挿管後は、チューブ位置を確認し、CO₂波形と胸郭の左右同時上昇をチェックします。
挿管が成功したら人工呼吸を開始し、手術中の麻酔維持に移行します。
各薬剤の特徴と看護師が押さえるポイント
| 分類 | 代表薬剤 | 特徴 | 看護のポイント |
|---|---|---|---|
| 鎮静薬 | プロポフォール | 速効性・制吐作用あり | 血圧低下・呼吸抑制に注意 |
| 鎮痛薬 | フェンタニル、レミフェンタニル | 強力な鎮痛作用 | 呼吸抑制・咳嗽反応に注意 |
| 筋弛緩薬 | ロクロニウム | 非脱分極性、作用時間短め | 投与前の換気確認が必須 |
| 拮抗薬 | スガマデクス | 筋弛緩を迅速に解除 | 適切な投与量を理解しておく |
【鎮静薬(静脈麻酔薬/催眠薬)】プロポフォール・チオペンタール・レミマゾラム
| 薬剤名 | 特徴・投与タイミング | 看護師向け重要ポイント | 作用発現時間 |
|---|---|---|---|
| プロポフォール | 最も頻用される静脈麻酔薬。導入・維持に使用。 | 血管痛あり → リドカイン・フェンタニルで予防。制吐作用あり。循環抑制に注意。 | 約10秒で鎮静、1分以内に作用発現 |
| チオペンタール | バルビツール酸系導入薬。導入時に使用。 | 蓄積作用あり → 維持には不向き。血管痛あり。 | 約10〜20秒 |
| レミマゾラム | 超短時間作用型ベンゾジアゼピン。導入・維持に使用。 | 拮抗薬フルマゼニルで覚醒可。高齢者でも安定。循環抑制に注意。 | 約10秒〜2分以内 |
💡看護のポイント:
導入時は血圧・SpO₂の低下、呼吸抑制に注意。
麻酔導入薬投与時は換気状態の確認とバイタル変化への即応が必須です。
【鎮痛薬(オピオイド)】レミフェンタニル・フェンタニル・モルヒネ
| 薬剤名 | 特徴・投与タイミング | 看護師向け重要ポイント | 作用持続時間 |
|---|---|---|---|
| レミフェンタニル | 超短時間作用。導入・維持に使用。 | 持続投与でのみ使用。効果切れが早く、術後鎮痛には不適。 | 超短時間 |
| フェンタニル | 導入・手術中・術後の鎮痛に使用。 | 導入時に血管痛緩和目的で使用される。呼吸抑制注意。 | 比較的短い |
| モルヒネ | 長時間作用。主に術後鎮痛に使用。 | 腎機能低下例で作用遷延に注意。嘔気・便秘の副作用。 | 長時間 |
💡看護のポイント:
オピオイドは呼吸抑制・徐脈・悪心嘔吐が代表的副作用。
特に導入・覚醒時は呼吸回数と二酸化炭素モニタを厳重に観察。
【筋弛緩薬】ロクロニウム・サクシニルコリン
| 薬剤名 | 特徴・投与目的 | 看護師向け重要ポイント | 拮抗薬 |
|---|---|---|---|
| ロクロニウム | 非脱分極性筋弛緩薬。全身筋弛緩を目的に使用。 | 挿管容易化目的で多用。呼吸筋も弛緩するため換気確認が必須。 | スガマデクス(即効性)、ワゴスチグミン |
| サクシニルコリン | 脱分極性筋弛緩薬。 | 悪性高熱症のトリガーとなるため注意。短時間作用。 | なし |
💡看護のポイント:
筋弛緩薬の作用が残存すると呼吸抑制や誤嚥のリスク。
覚醒時は筋弛緩モニタ(TOF)の確認と、拮抗薬投与の有無をチェック。
まとめ ― 麻酔導入の全体像から全身麻酔薬の投与順番を理解
麻酔導入から、麻酔維持・覚醒までの流れを意識しながら、看護師として観察・準備・対応すべきポイントを押さえておくことが重要です。
- 前酸素化で備える
- 鎮痛→鎮静→換気確認→筋弛緩→挿管の流れを意識する
- 各ステップで看護師が安全を見守る
これらを意識することで、麻酔導入時の不安や慌ただしさが軽減され、「なぜ今この薬を投与しているのか」が理解できるようになります。
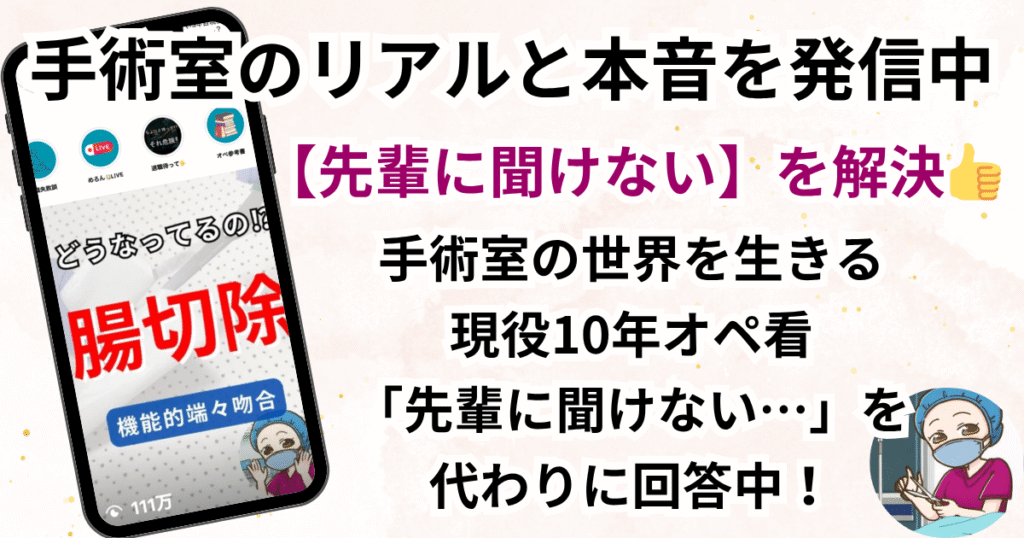
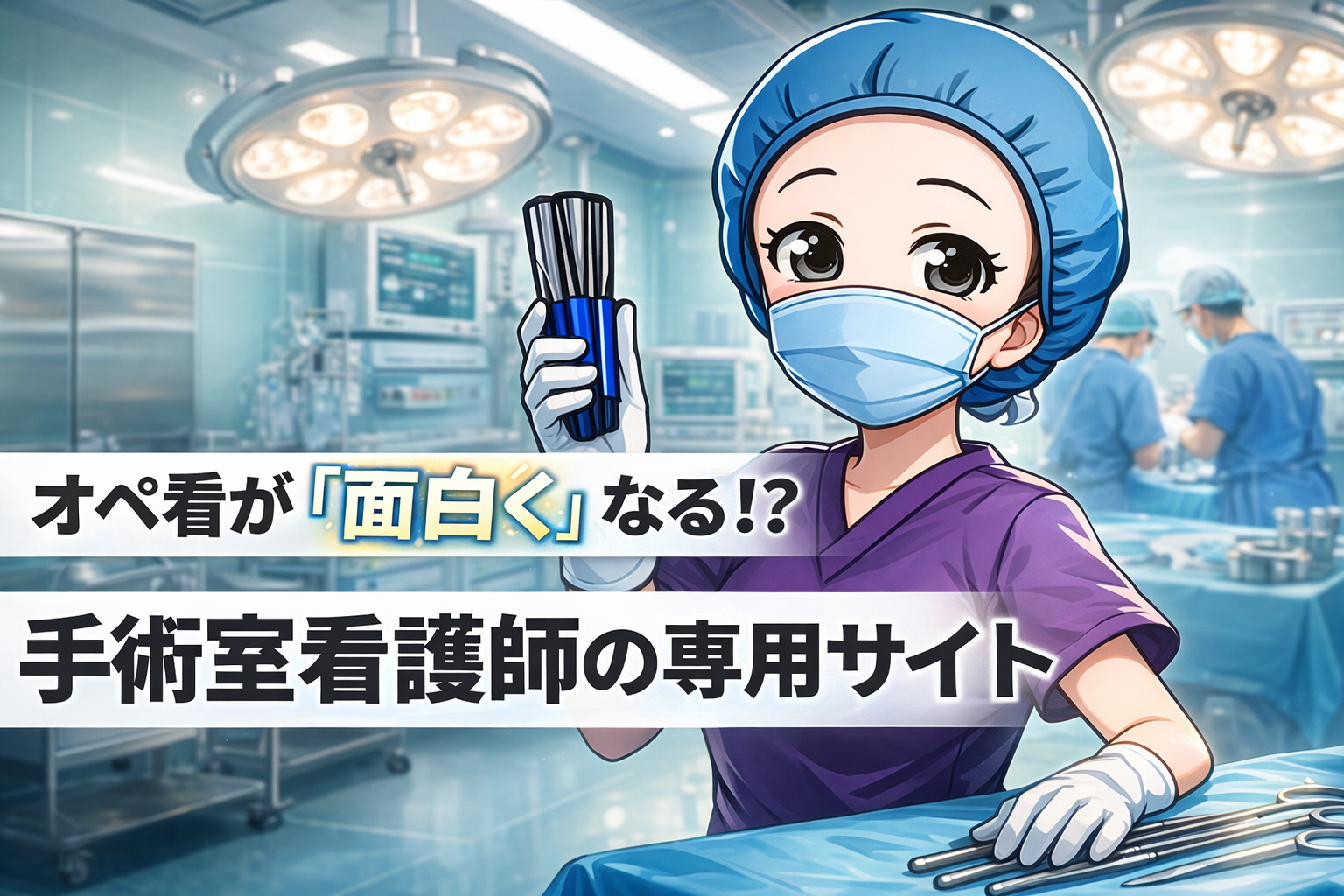
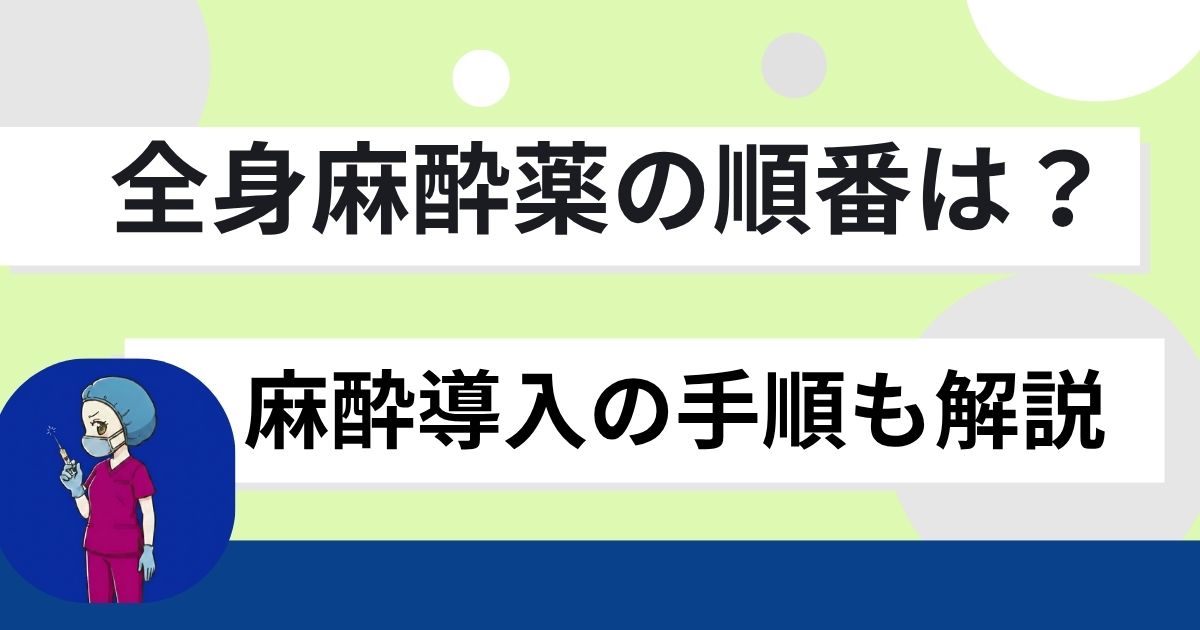
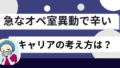
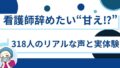
コメント